
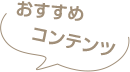
お役立ち情報
良好な血糖マネジメントに向けた食事療法と運動療法のコツをご紹介します。
監修:関西電力病院 総長 清野 裕 先生


生活習慣改善サポート情報
合併症を起こさない・悪くしないために、日常生活でできる糖尿病との付き合い方を紹介しています。

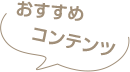
お役立ち情報
良好な血糖マネジメントに向けた食事療法と運動療法のコツをご紹介します。
監修:関西電力病院 総長 清野 裕 先生


合併症を起こさない・悪くしないために、日常生活でできる糖尿病との付き合い方を紹介しています。